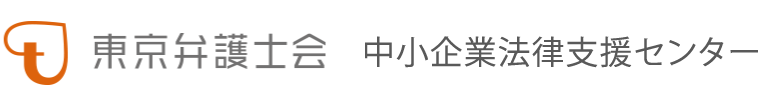経営お役立ちコラム
2025.03.26 【SDGs】
中小企業と従業員の人権
-SDGs の目標と尊重される人権及び法令遵守事項-
1 消費者に関するSDGs の目標と尊重される人権について
①サプリメントへの異物混入による健康被害発生(商品の安全性に関する問題)、②医学的な根拠のない効能を示した医薬品が出回り、その表示を信じて購入した消費者からの信頼喪失や、最悪の場合、消費者の身体・生命に対する被害発生(製品表示に関する問題)など、企業の提供する商品やサービスにより消費者の人権が害されるケースは、国内外を問わず深刻な課題となっています。また、近年は、①高齢者が複雑な契約内容を十分に理解できないまま不要な契約や不当に高額な契約の締結をしてしまうトラブル、②インターネットを通じて購入したサブスクリプション商品について、契約解除方法がサイトを見てもよく分からず契約を解除したいときに解除ができないトラブルなど、消費者と事業者の間にある情報量・交渉力の格差が拡大し、消費者が被害を受けるリスクが高まっています。インターネットを活用した商取引の問題としては、ステルスマーケティング(有名インフルエンサーによる商品紹介が、企業による宣伝広告であるにもかかわらず、インフルエンサー個人の感想であると消費者が誤認し、当該商品を購入するケース等)が近時注目を集めていたことと思われます。
企業がこれらの問題を放置すれば、①消費者からの信頼喪失による製品・サービスの購入減少、②従業員確保の困難(最近は、就職先企業の選択において、当該企業の人・社会・環境に対する取組みに関心を有している就活生も増えているといわれております)が生じ、当該企業は中長期的なビジネスを展開していくことができなくなることが予想されます。そこで、これらの問題は、企業が取り組むべき課題として認識されており、SDGs は消費者に関し、「3すべての人に健康と福祉を」「8働きがいも経済成長も」「10人や国の不平等をなくそう」「12つくる責任つかう責任」「16平和と公正をすべての人に」といった目標を掲げ、各課題の解決を図っています。
消費者の人権は世界的に比較的新しい権利で、日本国憲法にも消費者の権利を直接定めた条文はありませんが、消費者に対する深刻な負の影響が及ぶ場合には、個人の幸福追求権、生存権、財産権が害されることに繋がりえます。また、日本では、消費者基本法を制定して、消費者保護の重要性を訴えています。中小企業の経営者は、こうした消費者の人権に配慮し、人権課題の解決に取り組む必要があります。
2 消費者に関する法令遵守事項の概要について
消費者の人権に配慮した経営の実現のためには、まずはSDGsコンプライアンス(法令遵守)状況を確認することこそがその第一歩となります。日本では、下記のとおり消費者の人権を保護するための様々な法令が整備されています。
- (1) 安全な製品・サービスの提供(食品衛生法、薬機法、消費生活用製品安全法、製造物責任法等)
- (2) 適切な表示と広告(景品表示法、特定商取引法、独占禁止法等)
- (3) 不当・不正な勧誘活動の禁止(消費者契約法、特定商取引法等)
SDGsコンプライアンスの遵守により、消費者は安心して商品やサービスを購入できるようになり、ひいてはそのような取り組みをした企業に対する消費者の購買意欲が高まり、まさに「人が集まり選ばれる」会社へと成長していくことに繋がることが期待できます。このような消費者の幸福が会社の持続的発展に結びつく好循環こそが、消費者の人権を尊重する重要な意義であるといえるでしょう。
本記事について更に詳細なことを知りたい方は、書籍をご購読いただくか、中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
各記事は執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。