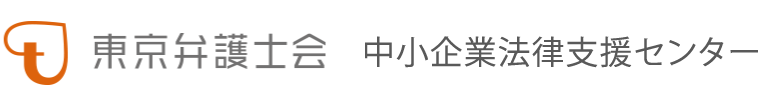経営お役立ちコラム
2025.03.26 【SDGs】
中小企業と従業員の人権
-B to C取引やD 2 C取引において消費者の信頼を得るために-
私たちが普段買い物をするコンビニや、普段利用する美容院、レストラン、旅行の際に利用するホテルなど、企業が、商品やサービスを個人(消費者)に提供するビジネスモデルをBusiness to Consumer(B to C)取引やDirect to Consumer(D2C)取引と呼びます。
近年、B to C取引やD 2 C取引の中でも、ECサイト事業(インターネット通信販売、レストラン、ホテル予約など)が著しく成長しておりますが、消費者による口コミが商品、サービスの売れ行きにも影響します。
そのため、B to C取引やD 2 C取引を展開する企業において、消費者の信頼を得られることが、事業を成功させる鍵といえます。
以下において、企業において消費者の信頼を得るための自主的取組事項の一例を、具体的取組事例を交えつつご紹介します。
- (1) 「安全な」商品・サービスの提供
商品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築していることは、消費者から見れば企業に当然求められるため、企業は、消費者に対して、自社の商品・サービスの安全性が確保されていることを客観的に示す必要があります。
例えば、国際標準化機構が制定する国際規格である「ISO規格」、一般財団法人製品安全協会が策定した安全基準・製品認証・事故賠償が一体となった「SGマーク」、一般社団法人日本玩具協会による「玩具の安全基準」である「STマーク」などを取得することで、消費者に自社商品・サービスの安全性をアピールすることができます。
加えて、商品の欠陥・サービスの不具合による事故が発生し、損害賠償義務を負うことに備えるためのものとして、PL保険への加入のニーズが増えています。
企業に対しPL保険への加入は義務付けられておりませんが、消費者の不安を払拭し、企業としても適切な対応を取るため、PL保険への加入は検討すべき事項といえます。 - (2) 「環境に配慮した」商品・サービスの提供
SDGsの達成に向けた取組みが増加する中、環境に配慮したサステナブルな商品への支持が増加しております。
例えば、ある子供服販売業を営む企業は、洋服のファスナーやボタン、ゴム製品について再生ポリエステル原料を使用し、商品を入れるポリ袋にはバイオマス(生物資源)由来の生分解されやすいプラスチックや、繰り返し使用できるエコパッキンを使用しております。
こうした環境に配慮した取組みは、SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」の達成に繋がります。
環境に配慮したサステナブルな商品に対する需要は高っていますので、これに応えるため、企業においても「環境認証マーク」(有機JASマーク、エコマーク、海のエコラベル、再生紙使用(R)マークなど)を利用してアピールをすることが重要です。
上記でご紹介した事項以外に消費者の人権との関係で自主的に取り組むべき事項はあります。更に詳細なことを知りたい方は、書籍をご購読いただくか、中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
ご利用にあたって
各記事は執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。