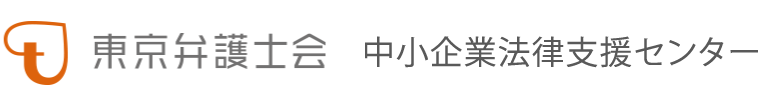経営お役立ちコラム
2025.04.23 【SDGs】
中小企業と取引先の人権
-取引先の従業員の人権を保護し、健全なサプライチェーンを維持・発展させていくために-
1 取引先に関する課題、SDGsの目標及び尊重されるべき人権について
経済活動は、原材料の調達から製造加工、在庫管理、配送、そして販売により消費者に提供されるまでの一連の流れ(サプライチェーン)から成り立っています。そして、サプライチェーンにおける直接の取引先企業においても、様々な資本力や規模の企業が存在しており、取引依存度などの関係性も多様です。
以下では、自社の資本力や相対的な規模の大きさ、取引依存度などを背景として、取引上の立場が弱い直接の取引先への不利益を与えることによる、取引先とそこで従事する従業員の人権に対しての負の影響を防止し、サプライチェーンを健全な形で維持・発展させていくための自主的取組事項の一例を、具体的取組事例を交えつつご紹介します。
-
(1) 取引先の従業員に対するハラスメント防止対策
例えば、自社の方が商品やサービスを購入する立場にあること等の立場の強さを利用して、取引先の担当者に、購入契約を締結することと引換えに性的関係を持つよう求めたり、取引先の担当者のわずかなミスを理由に暴言をぶつけたリするなど、取引の窓口となる従業員が、取引先の従業員に対してハラスメントを行う事例が問題になっています。取引先からすると、契約関係が解消されないようにとの配慮から、ハラスメントがなかなか明るみにならず、取引先の従業員が深刻な人権侵害を被る事態に立ち至ることがあります。
このような事態は、取引先の従業員が人権侵害を被るだけではなく、トラブルが表面化した際には、円滑な取引が阻害されることとなったり、訴訟リスクを負うことにもなりかねません。
そこで、このような事態を防止するためには、ハラスメント防止の対策(ハラスメント禁止の方針の明碓化と従業員への周知・啓発、ハラスメントの相談担当を設置する、ハラスメントが発生した場合には事実閑係の調査を行い、被害者に対する配慮措置を講じるなど)を取る必要があります。 -
(2) 契約書の作成・遵守
中小企業においては、契約書を作成せずに取引に入ってしまうケースが多くみられます。しかし、仕様や作業範囲、代金・報酬や納期など、取引条件が曖昧なままで取引を開始すると、取引条件に関するお互いの理解の違いが生じ、トラブルになりかねません。
例えば、ある住宅リフォーム業を営む中小企業が、過去に、戸建住宅のリフォームを受注した際、注文主からの仕様変更の申入れについて口頭のみで合意してしまった結果、変更内容について、注文主、下請け先と自社との間で理解の違いが生じ、訴訟にまで発展するトラブルになってしまったことがありました。そこで、当該会社は弁護士とも相談しながら、その後の案件については、請負契約書を作成して取引条件や仕様を明確にするとともに、契約締結後の変更の際も注文主と下請け先双方との間で確認書面を作成して変更内容を相互に確認する体制を作りました。これに併せて、納期や仕様等の変更の際には、仕様変更に要する具体的なスケジュールを踏まえて、注文主と交渉を行うなどして、下請け先に不利益が及ばないよう配慮もするようになり、トラブルになるリスクを著しく下げることができました。
こうした取組みは、自社がトラブルに巻き込まれる事態を予防するだけなく、注文主、下請け先や弁護士との間で前向きなパートナーシップ連携を構築する、まさにSDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に貢献し、健全なサプライチェーンを維持・発展させる事業のサステナビリティに資するものといえます。
上記でご紹介した事項以外にも、取引先の従業員の人権との関係で自主的に取り組むべき事項はあります。更に詳細なことを知りたい方は、書籍をご購読いただくか、中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
ご利用にあたって
各記事は執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。