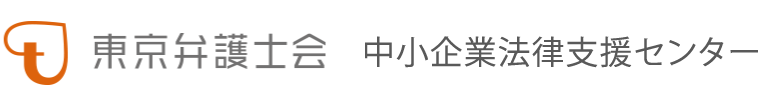経営お役立ちコラム
2025.10.29 【経営危機Q&A】
下請取引に関する各種Q&A(下請法関連)
※ なお、法改正(令和8年1月1日施行予定)によって、下請法の正式名称である「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改められ、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」等に改められる予定です。
-
Q1.
商品・製品や成果物を指定の納期に納入しようとしたら、「競合他社の台頭によって、売上が落ちている。そのため、仕入れ等をやめたい。」との理由で、親事業者側の都合で受領を拒否されてしまいました。どうすればよいのでしょうか。 -
A1.
まず、取引内容や取引当事者の資本金額1によって、当該取引が下請法の適用対象となる場合があります。そして、下請法が適用され、当該親事業者(下請法が適用される取引の発注者や委託者などの立場にある事業者。以下同じ。)の行為が下請法に違反する場合、公正取引委員会からの調査や勧告の対象となり得ます(以下、「下請法に関する一般論」といいます。)。
かかる下請法に関する一般論を踏まえて、本設例をみますと、親事業者による受領拒否の事案ですので、下請法4条1項1号(「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと」)に違反するかが問題となります。 公正取引委員会が公表している下請法に関する運用基準(https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html)によると、かかる「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして下請事業者(下請法が適用される取引の受注者や受託者などの立場にある事業者。以下同じ。)の給付の受領を拒むことが認められるのは、下請事業者の給付の内容が3条書面(下請法3条の規定に基づき下請事業者に交付しなければならない書面)に明記された委託内容と異なる場合や下請事業者の給付に瑕疵等がある場合等の極めて限定された場合のみですので、今回の「競合他社の台頭」は、「下請事業者の責に帰すべき理由」が該当しないと考えられます。
そのため、本設例の親事業者の行為は下請法に違反すると考えられますので、下請事業者としては、①下請法違反を指摘した上で、成果物の引取りを求める、②公正取引委員会又は中小企業庁に相談・申立てをして調査や勧告を促す、という手段が考えられます。ただし、これらの対応をとることにより、親事業者との継続的取引関係をむしろ悪化させ、最悪の場合、取引関係が終了するなど、結果として下請事業者の利益とならない可能性があることも留意する必要があります(このように、下請法所定の禁止行為に該当する行為を親事業者がした場合に、下請事業者がその事実を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、取引数量を削減したり、取引停止などの不利益な扱いをすることは、下請法4条1項7号が禁止する報復行為に該当します。そのため、仮にこのような取り扱いを受けた場合、下請事業者としては、取引数量の回復や契約継続を求める等の交渉を行うことの他、再度の調査等を公正取引委員会に求めるという措置が考えられます。)。
なお、下請法の適用対象とならない独占禁止法が定める優越的地位濫用に該当する可能性もあります。また、本取引に関して、親事業者に信義則上の受領義務が認められる場合には、契約解除や損害賠償請求の余地もあります。 -
Q2.
成果物を指定の納期に納入したのに、親事業者から、「競合他社の台頭によって売上が落ちたことで、資金繰りが厳しくなった。」との理由で、報酬が約束通りに支払われていません。どうすればよいのでしょうか。 -
A2.
まず、代金・報酬の支払遅延ですので、訴訟提起、仮差押え、担保権実行、連帯保証人への請求、相殺等の種々の債権回収手段を検討する必要があるでしょう。
また、下請法という観点からすると、上記1の一般論を踏まえて、本設例をみますと、親事業者による支払遅延の事案ですので、下請法4条1項2号(「下請代金を支払期日の経過後なお支払わないこと」)に違反するかが問題となりますが、本設例では、同条に違反するものと考えられます。なお、下請法2条の2により、下請代金の支払期日は、「給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない」とされています。
そのため、下請事業者としては、①下請法違反を指摘した上で、契約で定めた報酬の支払を求める、②公正取引委員会又は中小企業庁に相談・申立てをして調査や勧告を促す、という手段が考えられます。ただし、上記1の取引終了等の不利益の可能性には留意する必要があります。
なお、下請法の適用対象とならない独占禁止法が定める優越的地位濫用に該当する可能性もあります。 -
Q3.
親事業者により、「競合他社の台頭によって売上が落ちたことで、資金繰りが厳しくなった。」との理由で、当初提示されていた報酬や契約書に記載のあった報酬を一方的に減額されました。どうすればよいのでしょうか。 -
A3.
まず、代金・報酬の一部不払いの事案ですので、訴訟提起、仮差押え、担保権実行、連帯保証人への請求、相殺等の種々の債権回収手段を検討する必要があるでしょう。
また、下請法という観点からすると、上記1の下請法に関する一般論を踏まえて、本設例をみますと、親事業者による一方的な下請金額の減額の事案ですので、下請法4条1項3号(「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」)に違反するかが問題となります。
この点、親事業者が下請事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず下請代金を減額すれば、下請法違反となります。また、「歩引き」や「リベート」等の減額の名目、方法、金額の多寡を問わず、発注後どの時点で減額しても下請法違反となります。
そして、下請法に関する運用基準によると、かかる「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして下請代金の減額が認められるのは、下請事業者の給付の内容が3条書面に記載された委託内容と異なる場合や下請事業者の給付に瑕疵等があるとして受領拒否や返品ができるような場合に限定されています。
そのため、本設例の親事業者の行為は、下請法に違反すると考えられますので、下請事業者としては、①下請法違反を指摘した上で、満額の支払を求める、②公正取引委員会又は中小企業庁に相談・申立てをして調査や勧告を促す、という手段が考えられます。ただし、上記1の取引終了等の不利益の可能性には留意する必要があります。
なお、下請法の適用対象とならない独占禁止法が定める優越的地位濫用に該当する可能性もあります。 -
Q4.
継続的に取引をしている親事業者から、「競合他社の台頭によって経営が悪化して、今後は、これまでどおりの報酬を支払うことができない。」との理由で、報酬の引下げを要求されました。応じなければならないのでしょうか。 -
A4.
上記1の下請法に関する一般論を踏まえて、本設例をみますと、親事業者による取引代金の引き下げの事案ですので、下請法4条1項5号(「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」)に違反するかが問題となります。
この点、下請法の同条項の「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種又は類似の給付について当該下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価を指します。ただし、通常の対価を把握することができないか又は困難である給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請代金の額や労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の著しい上昇を反映せず据え置かれた下請代金の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」として取り扱うこととされています。
そして、買いたたきに該当するかどうかは、ⅰ)対価の決定方法(下請代金の額の決定に当たり、下請事業者と十分な協議が行われたかどうかなど)、ⅱ)対価の決定内容(差別的であるかどうかなど)、ⅲ)通常支払われる対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況、ⅳ)当該給付に必要な原材料等の価格動向などの要素を勘案して総合的に判断することになります2。
本設例の親事業者の行為について、下請法違反になるかどうかはこれらの事情を勘案して判断することになりますが、仮に違反するという判断になった場合、下請事業者としては、①下請法違反を指摘した上で、報酬の引下げには応じられない旨回答する、②公正取引委員会又は中小企業庁に相談・申立てをして調査や勧告を促す、という手段が考えられます。ただし、上記1の取引終了等の不利益の可能性には留意する必要があります。
なお、下請法の適用対象とならない独占禁止法が定める優越的地位濫用に該当する可能性もあります。 -
Q5.
親事業者から、「競合他社の台頭によって売上が落ちたことで、資金繰りが厳しくなった。」との理由で、報酬支払のため、支払サイト180日の手形を交付されました。しかし、このような長期サイトの手形ですので、金融機関で割引ができず、通常の割引よりも高い割引料でファクタリング業者に買い取ってもらいました。このような手形を交付することは許されるのでしょうか。 -
A5.
上記1の下請法に関する一般論を踏まえて、本設例をみますと、割引困難な手形が交付されている事案ですので、下請法4条2項2号(「一般の金融機関・・・による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること」)に違反するかが問題となります3。
かかる割引困難な手形とは、一般的に、その業界の商慣習、親事業者と下請事業者との取引関係、その時の金融情勢等を総合的に勘案して、妥当と認められる手形期間(現在の運用上、繊維業は90日、その他の業種は120日とされています。)を超える長期の手形のことをいいますので、本設例の手形は、これに該当すると考えられます。
そのため、本設例の親事業者の行為は、下請法に違反すると考えられますので、下請事業者としては、①下請法違反を指摘した上で、割引困難な手形の受領を拒否し、別の支払手段による対価の支払を求める、②公正取引委員会又は中小企業庁に相談・申立てをして調査や勧告を促す、という手段が考えられます。ただし、上記1の取引終了等の不利益の可能性には留意する必要があります。
なお、結果的に下請事業者が手形の割引を受けることができなかったときは、下請代金の支払があったとはいえないため、支払遅延(下請法4条1項2号)にも該当する可能性があります。 -
Q6.
親事業者から、「急に大きな仕事が入ったため人手が足りない。」との理由で、無償で自身の営業活動を手伝うように要請されましたが、これには従わなければならないのでしょうか。 -
A6.
上記1の下請法に関する一般論を踏まえて、本設例をみますと、不当な経済上の利益の提供要請がされている事案ですので、下請法4条2項3号(「自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること」)に違反するかが問題となります。
この点、下請法では、親事業者は、下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることは許されないとされ、また、経済上の利益は、協賛金、従業員の派遣等の名目は問わず、下請代金の支払とは独立して行われる金銭等の提供をいいます(なお、下請事業者が経済上の利益を提供することが製造委託等を受けた物品等の販売促進につながるなど自社にとっても直接の利益となる場合、その提供によって得ることとなる直接の利益の範囲内であるものとして、下請事業者の自由な意思により提供する場合には、下請法違反とならない点には注意が必要です。)。
そのため、本設例の親事業者の行為は、下請法に違反すると考えられますので、下請事業者としては、①下請法違反を指摘した上で、設例のような要請の中止を求める、②公正取引委員会又は中小企業庁に相談・申立てをして調査や勧告を促す、という手段が考えられます。ただし、上記1の取引終了等の不利益の可能性には留意する必要があります。 -
Q7.
長年継続的な取引が続いている親事業者から、「競合他社の台頭によって経営が悪化して、今後は、これまでどおり取引をすることができない。」との理由で、一方的に何の補償もなく契約を解除されてしまいました。取引の継続を求めることはできるのでしょうか。 -
A7.
まず、親事業者との基本契約書が契約解除・解約について定めていればそれに従うことになるため、第一に基本契約書の有無や内容を確認しましょう。基本契約書に契約解約についての定めがある場合はそのルールに従うことが基本になります。
他方で、基本契約書に契約解約についての定めがない場合、契約書を根拠として救済を求めることはできないものの、裁判例上、(準)委任契約・請負契約を問わず、取引が相当期間にわたり継続し、下請事業者が当該取引のために相当程度の資本を投下している等、下請事業者と親事業者との間に継続的な契約関係が存在する場合には、契約の解除に正当な理由または一定期間の予告が要求されることがあります。
もっとも、仮に、正当理由に該当しないとして解除が無効と判断されたとしても、契約書において最低発注数量などの定めがない限り、取引が続いている中でどの程度の発注をするかは親事業者の自由であるのが原則ですので、親事業者が発注を停止してしまう可能性はあります。その点は留意する必要があるでしょう。
また、継続的契約の解除に関する裁判例では、同時に損害賠償請求の可否及び金額も争点となっていて、数カ月分から1年間の利益にあたる損害の賠償請求を認容しているものがあります。そこで、取引継続を求めた上で、仮に取引継続が難しければ、金銭賠償を求めるという考え方もあり得ます。
なお、請負契約の場合の注文者による完成前解除(民法641条)、(準)委任契約の場合の無理由解除(民法651条1項)が存在する(これらの場合は解除が認められてしまう)ことにもご留意ください。
- 1 令和8年1月1日施行予定の改正法では、資本金基準のほか、従業員数基準も導入されることになっています。
- 2 買いたたきと関連し、令和8年1月1日施行予定の改正法では、対等な価格交渉を確保する観点から、下請事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、親事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して、下請事業者の利益を不当に害する行為を禁止する規定が新設されます。
- 3 令和8年1月1日施行予定の改正法では、下請法が適用される取引の支払手段として、手形払を認めないこととされ、また、電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては認めないこととされています。
ご利用にあたって
各記事は執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。